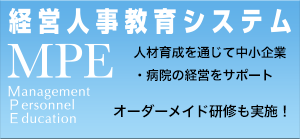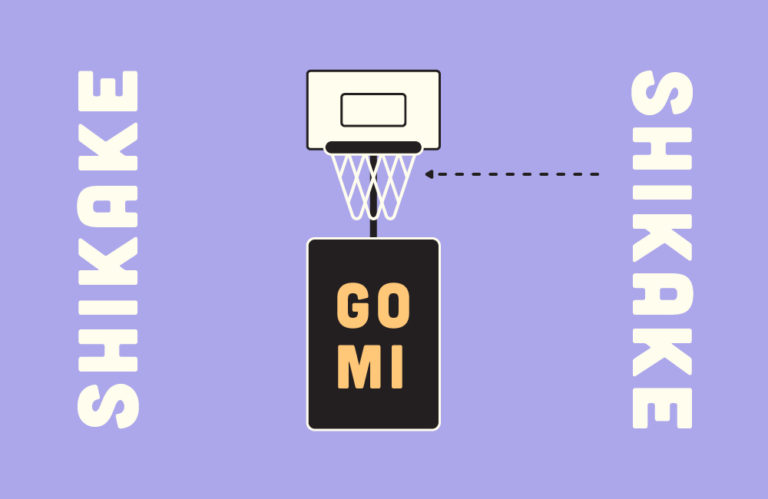
みなさんこんにちは。下ちゃんです。令和4年11月12日土曜日です。
#目標管理 #1on1面接 #人事制度設計 #組織診断 http://www.mpe-kobe.jp/?p=1921
#人事 教育 研修http://www.mpe-kobe.jp/?p=1916
11月20日に行われる神戸マラソン。「世界一ランナーマナーのよい大会」にしようと、県立御影高校の陸上競技部34人がマナーアップ隊に任命されたというニュース。
これくらいだったらいいかと勝手に自分の判断で捨てるなど基本的なマナーが忘れがちになっている昨今、このような高校生がマナー順守を呼びかけるというのはいいことですね。
「ポイ捨ては、マナーも一緒に捨ててるよ」っていう標語も作っていい経験になりますね・・・・・
さて昨日の続き、
自己肯定感を高めるために言葉、話し方、コミュニケーションの「見える化」が必須となってきています。
つまり、「いかに話すか?」「いかに伝えるか?」が人間関係を作っていくための大きな要素となっているのです。
「いかに話すか?」が大きな課題として、人間関係がうまくいっている人は、どんな話し方をしているのだろうか?中身を探ってみたいと思います。
話すことへの苦手意識を持ってしまう原因・・・・・
「人前で話したとき、急に頭が真っ白になってしまった」
「何を言っているのかわからない、と言われて自信をなくした」
「声が小さい、と言われてどうしていいのかわからなくなった」
こうした苦い経験が元となって、「自分は話すのが苦手」と思い込んでしまっている人は少なくないのでは・・・・・これは、話し方における自己肯定感が失われてしまっている状態です。
あまり知られていませんが、自己肯定感をなくしてしまったメンタルの状態を「自己否定感」と言います。
健全な自己肯定感を持つことは、自信の源になります。裏を返せば「うまく話せない」「いい人間関係を築けない」は、自己否定感の元にもなりうるのです。
一度や二度の失敗で「話すことが苦手」という強迫観念を持つ必要はまったくないのです。
しかし「話すことが苦手」と思い込んでいる人の多くは、数少ない失敗や心ない誰かの指摘が原因となって、話すことに苦手意識を持ってしまっています。
そんな人も、自分をラクに楽しく肯定できれば、確実に話し方はうまくなっていきます。
また、人間関係も今よりずっとラクに、良好になっていきます。