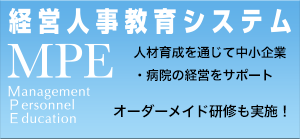みなさんこんにちは。下ちゃんです。令和5年5月16日火曜日です。
#目標管理 #1on1面接 #人事制度設計 #組織診断 #リカレント教育 #面談力
https://www.mpejinji-club.jp/366 https://www.mpejinji-club.jp/jinji
AI(人工知能)が人間の仕事を奪ったり、民主主義を脅かしたりするのでは・・・・と広がるリスクを懸念している記事が載ってました。
チャットGPTなど新たなAIの台頭によって倫理面でのリスクが懸念されており、専門家も当面はないと考えてきた社会へのリスクが早い段階で生じうる状況になったと警鐘をならしている。
今後の動向を注視したいところです。
さて、
今日もコミュニケーション能力を高めるためには、具体的にどういった手法があるのか見ていきましょう。
伝える力を高めるために代表的な手法として挙げられるのがPREP法というものがあります。
これは、Point(導入結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(最終結論)の順番で話を伝えるコミュニケーション手法であり、結論から先に話すことで、伝えたい内容が簡潔に伝わりやすくなるため、円滑なコミュニケーションが実現できます。
次は、相手の気持ちや感情に寄り添いながら話を聴く傾聴力を高める手法として、バックトラッキングというものがあります。
これは、相手の話した内容をオウム返しのように繰り返す手法です。「はい」、「ええ」、「なるほど」といった相槌に加えて、バックトラッキングを交えることで相手に対して「きちんと聞いている」ことを伝えられます。
お互いに理解を深めるためには、適度に質問を交えることも効果的です。一口に質問といっても、相手に自由に答えてもらうオープンクエッションと、「はい」、「いいえ」のように答えを限定したクローズドクエッションがあります。
オープンクエッションは相手から多くの情報が得られ話題を広げやすいメリットがある一方で、話をすることが苦手な人にとっては負担に感じ、有効ではないといったデメリットがあります。
対してクローズドクエッションは、相手に負担をかけることなく会話をリードできるといったメリットがありますが、聞きたいことしか聞けない、話題が広がりづらいといったデメリットもあります。
質問力を高めるためには、オープンクエッションとクローズドクエッションをうまく使い分けることが重要です。たとえば、相手の考えや意見が曖昧でわかりにくい場合には、「Aについて、このような解釈で間違いないでしょうか?」といったクローズクエッションを投げかけてみましょう。
コミュニケーションをとる際に感情的になってしまうと相手が萎縮してしまい、本音を話しにくくなることも考えられます。そこで有効なのが、怒りの感情をうまくコントロールするアンガーマネジメントです。
アンガーマネジメントは怒ることそのものを否定するのではなく、沸点に達した怒りの感情を抑え冷静さを取り戻すことを目的としています。
怒りの沸点は6秒とされているため、怒りの感情が湧いてきたら深呼吸をしながら6秒数え、気持ちを整理することで冷静さを取り戻すことを心がけましょう。
円滑なコミュニケーションには、相互理解を深め信頼関係を構築することが重要です。自己理解・他者理解・相手に合わせた関わり方という3つのステップを経ることで、相互理解は深まっていきます。
改めて、自己理解とは自分自身の思考や感じ方、行動特性を知ることで、他者理解とは相手の思考や感じ方、行動特性を知ることです。
そして相手に合わせた関わり方とは相手と自分との違いを認識し、受け容れたうえで相手に合わせたコミュニケーションをとること
自己理解ができていると、自分の良い部分とそうでない部分を受け容れ、自身をコントロールすることができます。さらに、他者理解もできていれば、相手と自分との違いを客観的に認識し、受け容れることでコミュニケーションギャップを減らすことにもつながります。
一度考えてみるものいいかもしれませんね・・・・